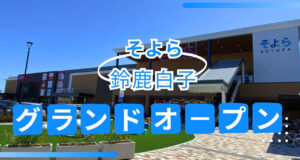皆様こんにちは。東海地方で主に風景写真などを撮影している あーる と申します。前回の【中区昭和区鶴舞】エリアの僕の記事、もうお読みいただけましたでしょうか?
↓↓↓前回の記事はこちらから↓↓↓
今回スポットを当てるのはJR武豊線「亀崎」駅周辺です。名古屋も中心部にお住まいの方だとなかなか馴染みのない地区だとは思いますが、亀崎を含めた半田エリアでは「知らないなんてもったいない!」と思わず言いたくなってしまうくらい山車祭りが多く開催されます。
特に半田の春祭りのトリを飾る亀崎地区の『亀崎潮干祭』はおすすめで、毎年8万人ほどの人が集まる超人気山車祭りです。
今回はそんな『亀崎潮干祭』の魅力をお伝えすべく、AM7:00代に現地入りして一日プログラム追いかけてきました!
僕が捉えてきた”亀崎潮干祭”の様子、ぜひ最後までご覧いただけたら幸いです。
令和6年 亀崎潮干祭
そもそも、亀崎潮干祭って?
詳しく語りだすとキリがないのですが、ざっくりと説明させていただくと神武天皇(天照大御神の孫であり初代天皇)が海からこの亀崎の地へ上陸したという伝説が残っているそうで、それにちなんで神の依り代である山車を浜へ曳き下したことが亀崎潮干祭の名前の由来とされています。
起源については諸説あるそうですがたどれば300年の歴史があるとのことなので、今日まで伝え続けられているというのは奇跡に近いお祭りだと思われます。
AM 7:00 神事はすでに始まっている
- ▲朝の空気を感じます
- ▲カモがゆらゆら気持ちよさそう
- ▲今回の舞台 亀崎港
- ▲朝早くから集まっています
- ▲立派な山車も揃い踏み
- ▲からくり人形が朝日を浴びて
日もまだ少し傾いているくらいの時間ですが、すでに山車はスタンバイ済み。それもそのはず、AM6:30から山車の祈祷があったためこの時間で既に一仕事終えた状態なのです。
- ▲先頭は東組 宮本車
- ▲朝一の待機時間は暇なのでしょうがないね…
- ▲公園で遊んでる子もいます。自由。
- ▲お店のお手伝い、えらいね。
曳き出しが始まるのはAM8:50。2時間くらい休憩や準備の時間となるので各々自由に過ごすことになります。
旧道沿いのお店も続々と店頭の準備を始めていて、もうすぐお祭りが始まるんだなぁというワクワクを肌で感じますね。
いざ、浜へ曳き出し
続々と人が集まり始め気づけば曳きだしの時刻。
スタートは東組宮本車から。山車祭り開始の瞬間ともあって、報道関係やテレビの取材カメラなど多くの方が集まってましたね。

談笑も交えつつ、威勢良い掛け声とともに山車が動き出します。
ちなみに「これから出発するぞー!」というときには必ず「カン!カン!」と拍子木の音が聞こえてくるので、それを合図に写真を撮る側としても気合をいれて臨みます。
- ▲おー!おはよぉ!といろんなところから聞こえてきます
- ▲拍子木を合図に続々と
- ▲若衆、がんばって!
- ▲セニアカーに乗っていても祭りの一員
少し先回りして、浜へ行ってみましょう。
- ▲なんだかすっかり夏だなぁと感じた瞬間
- ▲砂浜が気持ちいい
- ▲亀崎ゆえに亀モチーフ
- ▲ここへ山車が整列します
ありがたいことに快晴も快晴。日焼け止めを塗らなかったことを後悔するくらいの日照りです。
さて、一番手の東組が浜へ入ってきました。この五輌の山車が浜へ揃うまで少し休憩です。
一番の見どころ”海浜曳き下ろし”がスタート
- ▲意外と五輌揃うのに時間がかかるので、子供たちは飽きて浜遊びしたりしてます…笑
- ▲よく見ると子供を抱えながら綱を引くお父さんの姿もありますね。すごいな。
- ▲いざ曳き下し
- ▲先頭の引手は腰まで浸かってます
さて、ようやく水辺に全ての山車が揃っていったん休憩です。余談ですが昨年はこの時間に祭りに来られなかったため、この曳き揃えを見るために一年待ったことになります。
山車がこのように水辺に一列に揃えられるお祭りなんて、日本全国探してもここだけなのではないかと思いますね。

ラストの西組 花王車の曳き下ろしでは各組から若い衆が応援で勢ぞろい。力強く浜を進む姿は重さ約4トンだということを忘れてしまうほどでした。
曳き上げ~整列
全ての山車が縦に揃ったのち、今度はからくり奉納のため陸の広場へ再度整列します。ここからの曳き上げもまた大仕事です。
- ▲総動員
- ▲指令長の赤は美しい朱です
- ▲ものすごい力が加わってるんでしょうね
- ▲親子でしょうか。いいですよね、こういう瞬間
広場への曳き揃えが終わったところ。神社に白装束の神職の方が沢山いらっしゃいますね。
ここで神社へ向かいからくり人形の奉納が始まります。この間にからくり担当以外は昼食を摂ることになりますが、僕らカメラマンに休憩はありません。なぜならこの間全てがお祭りだからです。(半分冗談で半分本気です)
お昼休憩中に旧道を巡る
個人的には「お祭りも見どころを見たらはいさようなら」…というのはあまりにも勿体ない気がしています。その日、その時にしかないものはいたる所にあって、それも含めて楽しいのがお祭りの醍醐味だと僕は思っています。
そんなわけでふらりと旧道を巡りつつ、屋台で何かつまもうかという算段です。
- ▲お寺さんの参道が楽しい感じに
- ▲大きくわかりやすい看板
- ▲いくつになってもわくわくしちゃいます
- ▲なんか500円の方がお得に感じてしまう魔法
- ▲おたまもアリなのか…!
- ▲古民家を利用した洋食店
- ▲亀のイラストがかわいい
- ▲漁港とはいえ、おしゃれなお店も揃ってます
通り沿いにある『浄顕寺』では縁日が開催されていました。こちらも亀崎潮干祭に負けず沢山のお客さんで溢れてました。射的やスーパーボールすくいなんて、いかにも縁日って感じでうれしくなっちゃいますよね。
旧道沿いにはほかにもからあげやかき氷など、あまりにも魅力的な出店が沢山ありました。
500円で買ったレモンかき氷でキンキンした頭に、雄たけびに似た歌と手拍子が響いてきます。若衆が元気すぎる。
彼らが各地区の山車へ応援に行ってくれるおかげで、祭りが滞りなく進んでいると思うと頭が上がりません。
彼らのたくましい背中を追いかけつつ、また浜辺へ戻ります。ここまででやっと半分くらいなんですが、大丈夫でしょうか?(あまりにも写真が多くて誰ともなく問いたくなった)
祭り広場から曳き出し→大川曲げ場へ
神事などもはさみつつ、からくり人形の奉納が終わり曳き出し直前くらいの様子です。ずーっと盛り上がってます 笑
この後再度アナウンスがかかり、旧道沿いを南西へ向かい尾張三社を目指します。
AM7:00頃にいた場所まで戻ってきました。ここから尾張三社までは細い道が続き、大川曲げ場と呼ばれる場所まで結構な操舵技術が求められます。引き手の腕の見せ所ですね。
- ▲まだまだ序の口
- ▲そろそろギリギリ
- ▲軽自動車でギリギリくらいの道幅
見ているこっちがひやひやするくらいギリッギリのラインを通ります。あまりのギリギリっぷりに僕がビビッて手ブレしました。これが祭りの漢だ。
こちらが大川曲げ場第一カーブです。白線見ていただくとわかるんですが結構急です。これを4トンの山車が曲がっていこうとすると、相当な力が必要と思われます。
その後の第二カーブは僕のポジションがギリギリすぎて、エルボーでボディーブロー貰いました。名誉の負傷です。
第一カーブの後40mくらいでまた逆方向に舵を切らなければならないのでこれ自体が伝統技術『若手綱の早掛け』と呼ばれ今日まで伝わっています。

ここまで顔がゆがむくらい本気で力入れたこと、人生でありますか?
尾張三社への曳き込み
大川曲げ場を抜け、五輌揃っていよいよ終盤。尾張三社への曳き込みが始まります。一両ずつ神前まで曳き込み、終了後は後列まで曳き出しするのですが尾張三社の境内はとっても狭いのです。
高島屋前の金時計のあるエリアくらいと伝えれば広く思われるかもしれませんが、そこに鳥居と神社と見物客と山車&祭り関係者が一堂に会すわけですから、もうぎゅうぎゅうです。
- ▲子供たちも立派な戦力
- ▲狭いので綱は伸びに伸びて…
- ▲奥の奥まで入らないと神前に山車が来れません
- ▲曳き出し後、整列。これを五回
五輌整列
境内は暗所も多いため明るく撮影するので伝わりづらいですが、時刻はもうPM5:00を過ぎていてすっかり夕暮れの時間です。
曳き込みが終わり今度は曳き出しのタイミングでの一枚ですが、人の密集感が伝わりますでしょうか?
そして曳き出しの際、山車の整列にも先ほどの大川曲げ場での美学が適用されます。そう、ギリギリの美学です。

一台目に停車した左側の西組 花王車の横へ、ギリギリもギリッギリに停車する二台目の田中組 神楽車。あまりにギリギリすぎて歓声が沸きました。この凄さは五輌整列するとよくわかります。
ぱっと見はそれほどですが、二階部分の上山のでっぱりを見てみると、明らかにギリギリです。カッコよすぎるぜ…。
さて、無事に五輌揃って停車できた後は、再度からくり人形の奉納を経てサヤ納めとなるのですが、ここまでで二本あったカメラのバッテリーが底をつきましたのでこれにて終了です。
最後まで追いかけたかった気持ちもありましたが、この時点で活動時間は10時間を超え、総歩数は25000歩とさすがに自身の限界も感じてしまいました。
ちなみに最後のサヤ納めの時の写真は去年撮影してましたので、そちらを貼り付けて亀崎潮干祭を追いかける記事の締めとしたいと思います。夜の山車もカッコいいんですよ…。
さいごに
今回の記事、いかがでしたでしょうか?
文章の構成や密度はさておき、亀崎潮干祭の写真をここまでの物量で紹介する記事は他に類をみないのではないかなと思います。
僕は祭関係者でもなんでもないですが、それでもこの土地に伝わる山車祭りの凄さを、より多くの方に知っていただけたらなという思いで記事を書かせていただきました。
もし、この記事を読んで「このお祭りに行ってみたい!」と思う方がいらっしゃったら、それはとても嬉しいことだなと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!